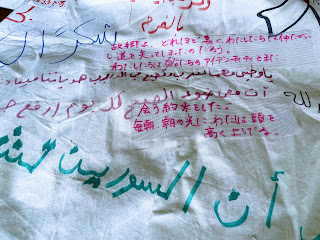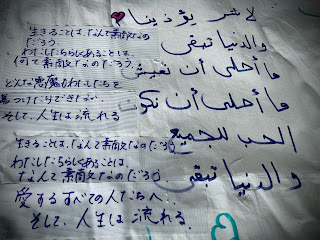ジョナス・メカスの映像を初めて観たのは
都美館の企画展の一角だった。
露出が高めで、色が飛んでしまいそうな
もしくは、室内で暗すぎて、影に埋もれてしまいそうな断片が
でもそこにしっかりと存在している光の中で、
大切な小さな石のように一つ一つ、大切に置かれていく。
日常のどちらかと言ったら、とりとめもないような映像が
切り取られ、続いていく。
見た瞬間に、たとえそれが
ただの道を歩く人々であったとしても
風に揺れる花々であったとしても、
食卓を囲む人々の姿であったとしても、
被写体のすべてに対する愛おしさに溢れている、そう
誰もがきっと感じるだろう。
こんな,宝石のような映像を撮る人がいるのか、と
ただずっと、流れる映像を見続けていた。

その印象が強かったから、「眩暈 VERTIGO」という映画が上映されるのを
随分と心待ちにしていた。
たまたま見に行った日、監督と共に、
吉増剛造氏も会場に来ていて、映画の中の断片を
聴くことができた。
NYでメカスの息子に会うシーン、そして
日本中のメカスファンの心が、自分の身体に乗り移って、
「メカスさーん」と呼びかける言葉が出てきた、と
身体と言葉が一体となったような、所作と佇まいで、話していた。
映画は期待通り、それ以上に良かった。
映像の場面一つひとつが美しかったし、
ジョナス・メカスへ抱く、吉増剛造の愛しさに
とにかく溢れていた。
歌を歌うのが好きだったメカスが、映画の中で、
言葉を音に乗せて、アコーディオン片手に歌う。
Dream of Humanityと繰り返す。
彼の映像の中にも、歌を歌う人々の姿が出てきて、
いつも誰かに向けて、自然に歌い出すような流れが印象的だったのだけれど、
フィルムを回す本人が、いつもそうやって歌っていたのか、と
ひどく合点がいく。
後半に出てくるパウル・ツェランの音声も、ひどく印象的だった。
自分の国から逃げねばならず、難民となった先で
母国語とは異なる言葉を操ることを課せられ
言葉という一番慣れ親しんだはずの表現方法が、一度
手の中から逃げていく。
それでも、ツェラン、メカスはそれぞれ、言葉やその周辺で表現を試みる。
ユダヤ人として、ナチス時代に強制収容所に収容され、
過酷という言葉では、とても表しきれない経験をして、
それが、その後の人生の流れと表現の核心を決定付けているところもまた、
共通するところだった。
けれども、映画の中で何が一番印象に残ったか、と訊かれたら、
圧倒的に、メカスの息子、セバスチャンの目、表情と答える。
メカスの最期の場面を尋ねる吉増剛造の姿を見つめる
セバスチャンの表情は、形容し難く、圧倒的な慈愛に満ちている。
気の小さい私は、海外で人と接する時、だいたいいつも、
どこか不安を抱えながら、おそるおそる、どんな人なのかと
その人の佇まいを凝視することが多かった。
そこから得られる情報の蓄積で、
安心できる人を経験的に、見分けていくことになる。
セバスチャンの顔は、会ったら一目で、
ひどく安心できると確信できる人の顔だった。
特に、吉増を見つめるまなざしが、
私がよく知っていて、大好きな人たちのまなざしと重なる。
あの人たちの顔を、よく訳もなく見つめていたのは、
ただ見ているだけで、心が落ち着くからだった。
映画を観ている時も、このまなざしをずっと眺めていたい、と
映画の主題の流れとは離れて、本能的に思う。
まなざし、には、客体である対象を見つめる視線がある。
同じくまなざす、という動詞にも、
対象を見つめる視線がある。
そして、その視線には、見る側の意識が介在する。
対象をどのように見るのか、という意志が反映された
視線としての、まなざし、なのだ。
だから、まなざしそのものに、まなざされる対象を
定義づけたり、意味づけたりする行為も、
場合によっては含まれることになる。
時に、そんなまなざしは、対象を縛ったり、決め付けたりもする。
だから、まなざしそのものに、功罪が存在することを
私たちは意識しなくてはならない。
けれども、セバスチャンのまなざしは、
その瞳の奥に、何かを決めつけるのではなく、
そのまま受け入れて、対象の心を映し出し、
まなざされた対象も意識していなかった
心の奥底の思いに気づかせる。
覗き込むものすべてを映す
凪いだ水面のようなまなざし。
もしかしたら、それはもはや哲学の文脈が意味する、
まなざしとは言わない、と捉える人もいるのかもしれない。
ただ私は、きちんと意志的な視線を携えて、
相手をまなざしている、と感じていた。
根底に、対象を愛しむ存在として捉えている、というのが
まなざしが携える、まなざす人の意志だ。
そのまま受け入れられていると感じられたならば、
対象の心は開かれる。
その心のうちが言葉にならなくても
表情や視線の中に、開かれた心の断片や気持ちが
細かな泡のように浮かび上がってくる。
そんなまなざしが生み出す、心と心の交流が
映画の中で、映像として記録されていた。
回り回って、それはまさに、ジョナス・メカスが
フィルムを通して持ち続けたまなざしだった。
「メカスさんが生涯がけて育てた、
奇跡的な作品と言っていいような人なのね」
息子セバスチャンについてそう語る、
吉増剛造の言葉を思い出す。
確かに、フィルムを通じて表現していたものを
息子はそのまなざしだけで、表現し尽くしていた。
目でものを語る時、
言葉にならない感情を、視線のうちに込めて
時に訴え、時に絶望し、時に怒り、時に苦悶する。
主体の感情が瞳に現れる。
おそらく、この時にまなざしは存在していない。
なぜなら、その時の目は、対象を見ることを放棄して、
たとえ目を見開いていたとしても、
心は感情の中に閉じこもっているからだ。
対象ありき、のまなざしが、
そのうちに、持てる幸な、愛しみを対象と分かち合おうとする。
もし対象が幸ではなくとも、そのまなざしに
いくばくかの幸を感じられる、そんな経験に
何度となく救われてきた気がする。
特に、言葉の通じない場所、言葉が掴み取れない場面で
まなざしから滲み出るものを
敏感に感じとって、なんとか生き延びてきた気もする。
まなざす人はその視線に愛しみなど、
別段意図して込めていなかったかもしれない。
それでも、慈愛を持って受け入れる、その人たちの在りようが
まなざしのうちに表れ、肯定されてきた。
私自身が、まなざす人間でもある。
いつか私も、
セバスチャンのようなまなざしを携える人間になって
今までいただいたたくさんの安心感を、
他者に感じていただける人になれるだろうか。